物流ドライバーの働き方改革を推進するべく、2024年4月からドライバーの労働時間の上限が定められるなど、さまざまな施策が実施されました。そして、それら法制度上の変更により、社会全体が許容できる総物流量が減少してしまうという問題がいわゆる2024年問題でした。
あれから1年が過ぎましたが、また来年2026年に比較的大きな制度上の変更があるということをご存知でしょうか。一部関係者の中ではこれら変更点について2026年問題と呼ばれていますが、今回のコラムでこの問題、すなわち2026年にどのような変化があるのかについてまとめたいと思います。
まず、この背景ですが、2024年問題により、トラックドライバーの労働環境改善により物流量が制限される中で、そもそもの物流業界全体の効率化が必要であると認識されることとなりました。
そこで、2025年4月より、流通業務総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)が施行されました。その内容は、物流事業者だけでなく、荷主(発荷主・着荷主)にも物流効率化のための努力義務を課す、というもので、その取り組み事項について国が判断基準を策定する、というものです。
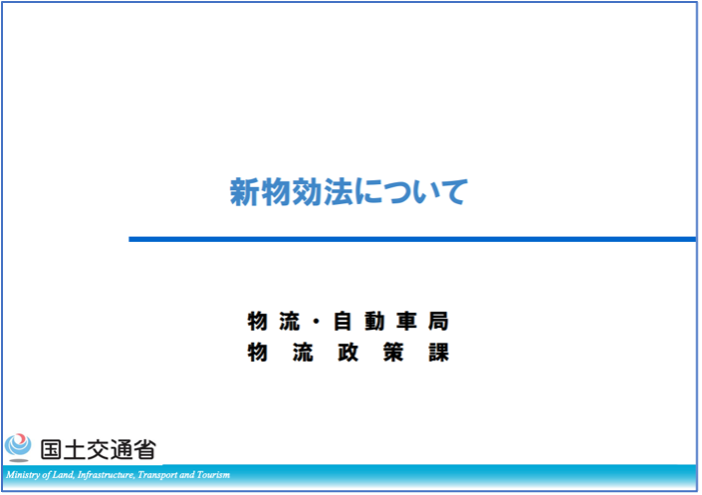
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001878512.pdfより引用)
そして、一年間の猶予を経たのち、2026年4月から一部企業(いわゆる特定事業者)については物流効率化のために、中長期計画の作成や定期報告が義務付けられることとなります。そして実際の実施事項が不十分な場合は国が勧告や命令を実施するものとされています。
※特定事業者は下記となります。(合計4000社程度)
①取扱貨物の重量が9万トン以上の特定荷主・特定連鎖化事業者(上位3200社程度)
②貨物の保管量が70万トン以上の特定倉庫業社(上位70社程度)
③保有車両台数150台以上の特定貨物自動車運送事業者等(上位790社程度)
要約すると、2025年の間は努力義務だけで良いのですが、2026年からは実際に書類の作成や提出義務が課され、運用上の負担が増大することとなります。
具体的に求められる取り組み事項としては、荷待ち時間短縮を目的としたトラック予約受付システムの導入や、積載効率の向上を目的とした配車システムの導入などがあります。

(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001878512.pdfより引用)
物流業務効率化のために
①中長期計画を策定する。
②専用システムを導入し、現状のオペレーションを改善する。
③システム導入による改善結果をまとめ、国に報告する。
という3ステップが必要となり、実際に現場のオペレーション変更を伴うことが必須となるため、特にシステム導入過渡期は現場の運用上の負担が一時的にでも増大することが考えられます。
もちろん、システム導入実施後、オペレーションに慣れてきた頃には導入以前に比べ物流効率化が進展すると考えられ、社会全体で考えても必要な変化ではあろうと思います。
多くの企業ではすでに一部システムを導入しつつ、物流効率化に向けて改善されておられますが、まだ実施されておられない企業様におかれましても検討いただければと思います。
